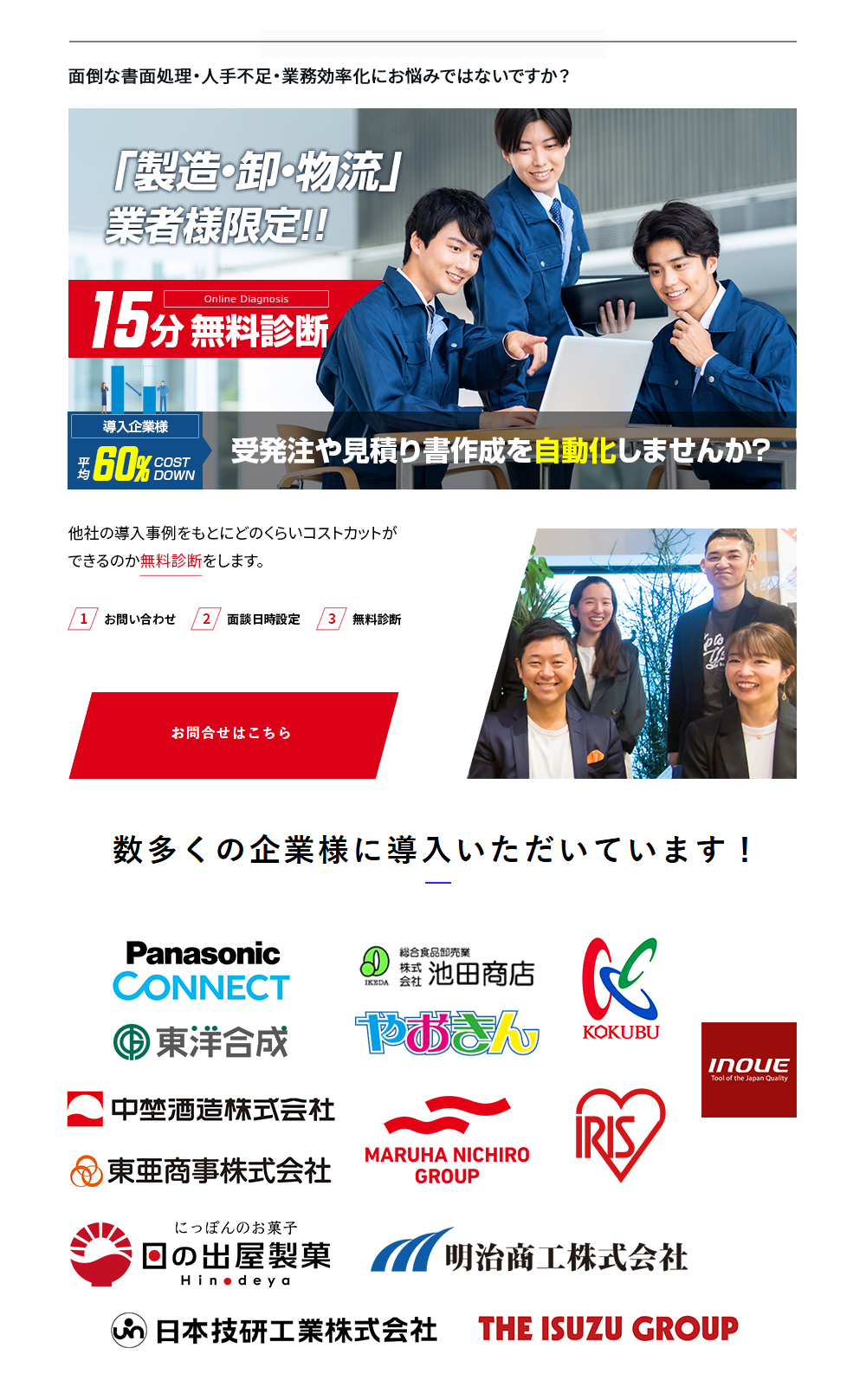コラム
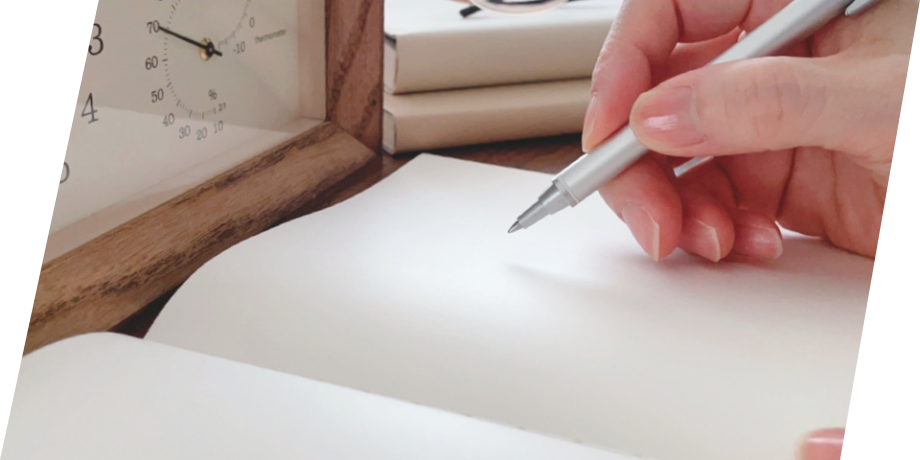
ai-ocr 使えない?製造業の現場が抱える課題と解決策

導入担当者の悩み:
「AI-OCRを導入したのに、手作業が減らない」「読み取り精度が低くて結局目視チェックが必要」「設定が難しくて現場で定着しない」──製造業の受注・発注業務を効率化したい担当者様の中には、このような声を抱える方が少なくありません。特に倉庫が郊外や海沿いにある場合、残業が常態化し、帰宅時の安全リスクや人材採用難が深刻化します。しかし、従来型AI-OCRだけでは現場の課題を解決しきれず、「使えない」と評価されるケースが増えています。本記事では、AI-OCRが「使えない」と言われる理由を整理し、製造業の現場特有の悩みを踏まえたうえで、受注業務特化型ソリューション「受発注バスターズ」による解決策をご紹介します。
1. AI-OCRとは?導入前に押さえたいポイント
AI-OCR(Optical Character Recognition)は、紙の帳票やPDFデータに含まれる文字をAIの力で読み取り、テキスト化・データ化する技術です。従来のOCRと比べて「手書き文字」「複数カラムの帳票」「傾いた画像」など複雑な書類にも対応しやすいとされています。製造業では受注書・発注書・納品書・検収書といった多種多様な紙帳票が発生し、人手で入力していると「ミスが発生しやすい」「工数が膨大になる」といった課題があり、AI-OCRへの期待が高まりました。
ただし、AI-OCRは万能ではなく、導入前に自社帳票で精度や対応範囲を確認しないと、「期待ほど使えない」と判断されることが多い点に注意が必要です。
2. 「使えない」と言われる主な理由
2.1 認識精度の限界
AI-OCRは98%前後の認識精度をうたう製品もありますが、実際には以下のようなケースで誤認識が発生します。
- 手書き文字のクセが強い場合
- 古いFAXやかすれた印字が混在する場合
- 複雑なフォーマットや特殊記号を含む書類
たとえば郊外倉庫で「手書きで記入した納品数量が薄墨になって読み取りができない」「FAX受信時に文字がぼやけ、AIが数字を誤認識する」など、誤読が続くと結局手作業で目視チェックが必要となり、「AI-OCRを導入した意味がなかった」と評価されてしまいます。
2.2 設定や操作の難しさ
多くのAI-OCRツールは帳票レイアウトごとのテンプレート登録が必須で、帳票ごとに「項目名」「文字の位置」を入力・紐付ける必要があります。製造業では取引先ごとに異なる注文書が数十~数百種類あるため、
- テンプレートを一つずつ作成する工数
- 帳票デザインが変更された際に再登録が必要
- ITに不慣れな現場担当者では操作/設定が難しい
といった理由で現場運用が混乱し、「テンプレート登録に時間がかかりすぎて使いきれない」「操作方法が分からず、誰もサポートできない」といった事態が起きます。
2.3 対応帳票の範囲が狭い
AI-OCR製品によっては定型フォーマットしか対応しないものがあり、製造業で頻繁にやり取りされる多様な注文書・伝票のうち、一部しか読み取れないケースがあります。「A社のExcelデータはうまく読み取れたが、B社の手書き伝票は対応外で手入力」「C社のPDFは文字がぶれて誤認識が多い」など、帳票がバラバラでは導入効果が半減し、現場から「使えない」と言われかねません。
2.4 コストとROI(投資対効果)のバランス
AI-OCR導入にはライセンス費用・サーバー費用・サポート費用が発生し、特に中小規模の工場では投資負担が重くなりがちです。さらに読み取り後の目視チェックが減らないと、人的工数削減効果が思うように得られず、「導入費用を回収できるのか不安」「高いお金を出しても効果が薄い」となるケースが多発します。
3. 製造業特有の現場課題とAI-OCRだけでは解決できない事情
製造業の受注担当者様が日々直面する課題を挙げると、以下のような状況が見られます。
3.1 郊外・海沿い倉庫の人手不足と安全リスク
郊外倉庫では「退勤時の公共交通機関が少ない」「深夜まで残業すると帰宅が不安」といった事情があります。夜間に一人で工場を出ることに不安を覚える担当者様も多く、残業が慢性化し安全リスクも高まります。AI-OCRを導入しても「読み取り精度が低いため結局夜間に手作業で修正」「人手が足りず入力が遅れる」となると、残業削減につながらず現場の不満が募ります。
3.2 属人化した受注処理
ベテラン担当者が「この会社は仕向地が違うから至急扱い」「この取引先は特別なコード体系を使う」といった頭の中の暗黙ルールで処理している場合、新人が入ってくると同じ水準の判断ができずミスが増えます。AI-OCRを入れても、学習すべきルールの登録が膨大になり、結果的に運用コストがかさむため、属人化を解消できず「AI-OCRは使えない」という評価に繋がります。
3.3 帳票設定の手間
製造業では自社独自デザインの手書き伝票や、取引先指定のフォーマットが数多く混在します。そのためテンプレートを作成し続ける手間が膨大になり、AI-OCRを導入しても「結局帳票を追加するたびに設定が必要」「取引先がフォーマットを変更すると再度登録が必要」という運用の煩雑さに直面します。これでは本来の「手間削減」は達成できません。
3.4 フォーマット統一の困難
製造業の商流では「仕入先にも取引先がある」「取引先がさらに別の取引先とつながる」ため、フォーマットの統一は極めてハードルが高いです。自社から「この書式に合わせてほしい」とお願いしても、取引先の社内事情や利害関係で断られることがほとんど。「AI-OCRを使うから全員このフォーマットにしてほしい」とは現場から言えず、結局多様な帳票が混在したまま運用せざるを得ません。
4. 現場でAI-OCRを「使える」に変える成功のポイント
では、これらの課題を踏まえたうえで、AI-OCRを現場で定着させ、使える状態にするには何が必要かを以下のように整理します。
4.1 自社現物帳票での精度検証を徹底
・実際に使う注文書・手書き伝票・FAX帳票を持ち込み、AI-OCRベンダーに読み取りテストを依頼しま しょう。
・認識率90%以上を目安とし、特に「手書き文字」「かすれた文字」「チェック欄」など現場でよく使う要素を試験的に読み取ってもらうことが重要です。
・帳票デザインが変更された場合は再テストを行い、実用レベルで運用できるかを都度確認します。
4.2 操作性とサポート体制を重視
・ドラッグ&ドロップだけでアップロードできる直感的操作や、読み取り結果を即座にプレビューできる機能があると現場定着が早まります。
・導入時の現場立ち会いサポートやチャットサポート・電話サポートが充実しているかを確認し、担当者が困ったときにすぐ相談できる体制があると安心です。
4.3 非定型帳票対応力をチェック
・テンプレート登録不要で自動判定できるAIエンジンを搭載している製品を選ぶと、帳票を一つずつ登録する手間を省けます。
・書類のレイアウトが変わってもAIが自動で学習・吸収してくれる機能があると、運用負担が軽減されます。
・手書き文字の判別精度が高いかをサンプル検証で確認し、誤認識を最小限に抑えられる製品を選びましょう。
4.4 既存システム連携と運用フローの明確化
・読み取ったデータを自社の受注管理システムや基幹システムに連携できるかを必ずチェックします。システム連携やCSV出力機能の有無を確認し、二度手間を生まない設計が望ましいです。
・現場の運用フローを見直して「誰がいつ読み取り結果をチェックし、どのタイミングでシステム連携するか」を明確化し、担当者間で合意を取っておくことで混乱を防ぎます。
4.5 投資対効果(ROI)のシミュレーション
・現状の手入力工数を洗い出し、「1件あたり何分かかる」「月間何件あるか」を把握します。
・AI-OCR導入後の処理時間を想定し、削減できる時間と人件費単価を掛け合わせて年間削減額を算出します。
・初期費用・月額費用を含めた総投資額と比較し、「1年目で回収できるか」「2年目以降にどれだけの利益効果が出るか」を数値化して資料に落とし込むと、決裁者への説得力が増します。
5. 製造業の受発注業務を根本解決:「受発注バスターズ」のご提案
製造業や物流業の受注担当者様が抱える「人手不足」「帰宅リスク」「属人化」「帳票設定負担」「フォーマット統一困難」といった課題を、AI-OCR単体ではなく受注業務全体の自動化で解決するソリューションが『受発注バスターズ』です。以下に主な特徴をまとめます。
5.1 テンプレート設定は必要、でも“丸投げ”で完結
『受発注バスターズ』では、帳票ごとにテンプレート(レイアウト情報)の設定が必要です。ただし、お客様側でテンプレートを作成・登録する必要はありません。
・取引先ごとの帳票レイアウトを弊社がすべて代行でテンプレート化し、納品時には「すぐに使える状態」でご提供。
・「この書類のこの位置に商品名がくる」といった読み取りの“クセ”も弊社側で設定済みのため、現場のご担当者様は帳票をアップロードするだけでOKです。
・帳票の新規追加や取引先のレイアウト変更があった場合も、随時サポートチームがテンプレート作成・更新を行うため、現場のITリテラシーに関係なく、継続運用が可能です。
つまり、「テンプレート設定は必要だが、現場には一切手間をかけさせない」仕組みです。これにより、AI-OCRツールにありがちな“設定の手間で挫折する”リスクを根本から解消しています。
5.2 現場のフローを変えずに使えるシンプル操作
・ドラッグ&ドロップだけで読み取り開始できる簡単な操作設計で、ITに不慣れな方でも直感的に操作可能。
・導入後のサポートが完備されており、短時間の教育で現場定着が進みます。
5.3 最大93%の工数削減で残業ゼロへ
・AIによる自動仕分けとマスタ紐付け機能で、人手で処理していた工数を大幅に削減します。
・ある製造業では、従来月100時間かかっていた受注入力がわずか7時間に短縮され、夜間残業がほぼゼロとなりました。
・人依存の属人化を排除し、社内の誰でも同じ品質で受注処理できる仕組みを構築。新人や派遣社員でもベテランと同じ精度で処理可能です。
5.4 人材採用難の緩和と安全確保
- 特定のベテラン社員しか使えなかった業務をシステム化し、休暇や離職による業務停滞を防止します。
- 残業時間の削減により夜間移動による自社スタッフの安全リスクも抑えられます。
5.5 費用対効果の高い投資
- 導入前に現状工数をヒアリングし、期待される削減時間と人件費を算出したうえでプランを作成。
- 初期費用・月額費用を含めたROI(投資対効果)シミュレーションを示すことで、導入1年目から黒字化を目指せます。
- 相談後、無料読み取りテストで自社帳票の読み取り精度を確認できるため、不安なく導入を検討できます。
6. まとめ:AI-OCRは「選び方」と「運用」で使えるツールになる
AI-OCRを「使えない」とする評価の多くは、精度・設定・コスト・現場運用のギャップから生じています。製造業の受注・発注業務では、多様な帳票が混在しITリテラシーが高くない担当者も多いため、従来型AI-OCRだけでは課題を根本解決できません。
本記事でご紹介したように、自社帳票の事前テストや非定型帳票対応力の確認、シンプルな操作性・サポート体制、他システム連携や運用フローの整備、費用対効果の明確化などを押さえることで、AI-OCRは本来の価値を発揮できます。
さらに、受注業務特化型ソリューション『受発注バスターズ』であれば、
- 帳票テンプレート登録不要
- 現場フローを変えずに導入可能
- 自動仕分け・マスタ紐付けで属人化を排除
- 最大93%の工数削減で残業削減
- 安全確保と人材採用難の緩和
といった特徴で、製造業の現場課題をワンストップで解決できます。まずはお問い合わせで自社帳票の読み取り精度や操作感をお試しください。AI-OCRを「使えない」とあきらめる前に、最適な解決策を選び、現場の受注業務を劇的に改善しましょう。
【お問い合わせはこちら】
受発注バスターズ導入に関するご相談:
https://batton.co.jp/lp/order-busters/
受発注バスターズ編集部
受発注バスターズ株式会社(旧:株式会社batton)は、AI搭載の業務効率化ツール「受発注バスターズ」やRPA「batton」の開発・提供を通じて、製造業・卸売業・商社の業務効率化とDXを支援しています。
「誰もが、仕事を遊べる時代へ。」をミッションに掲げ、属人化の排除や作業の自動化によって、人手不足やミスの多発といった現場の課題解決に取り組んでいます。
- 会社名:受発注バスターズ株式会社(旧:株式会社batton)
- 設立:2019年8月14日
- 所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目5-4 NOVEL WORK 京橋 3F
- 公式サイト:https://batton.co.jp/
※本記事は「受発注バスターズ編集部」が執筆・監修しています。