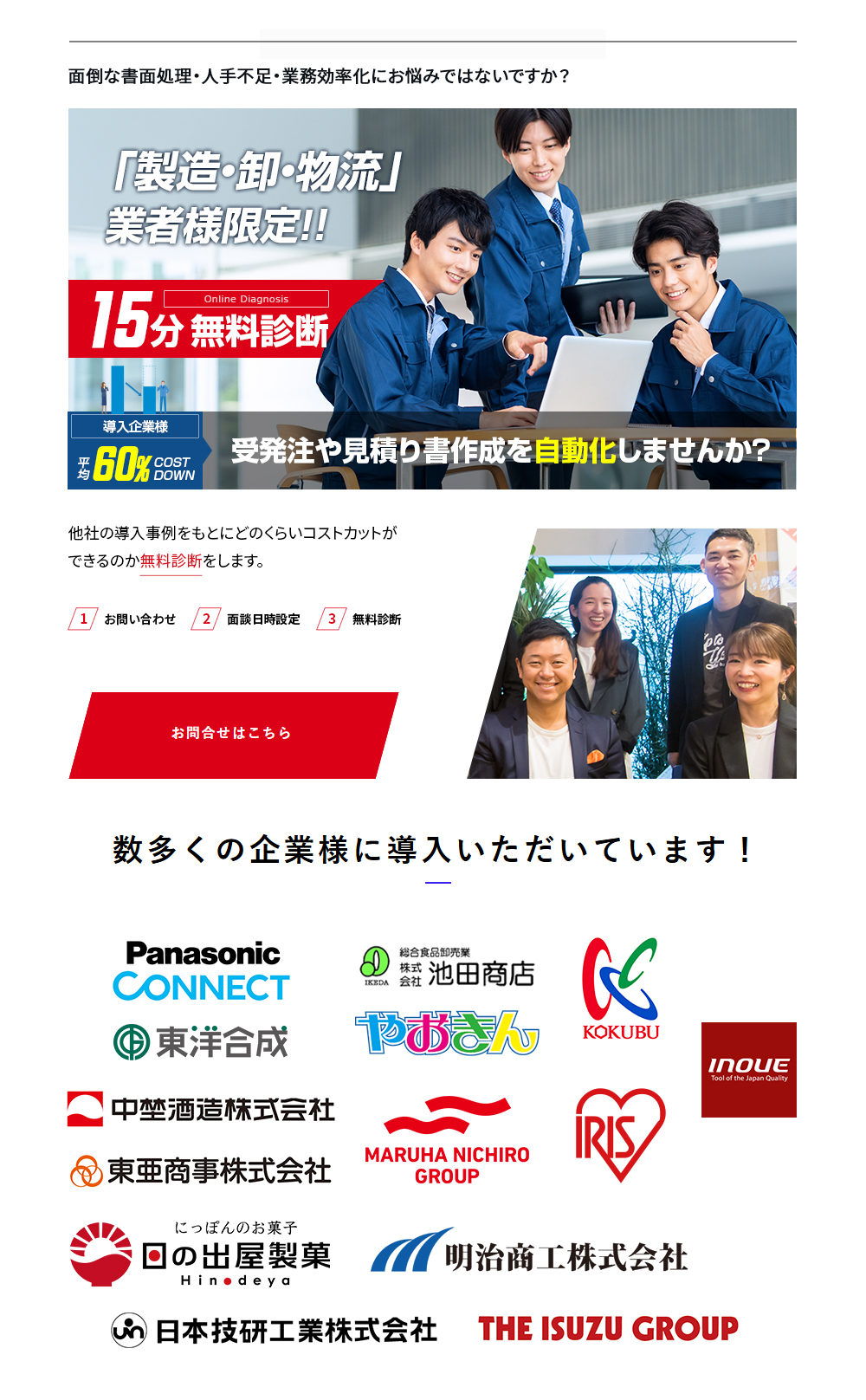コラム
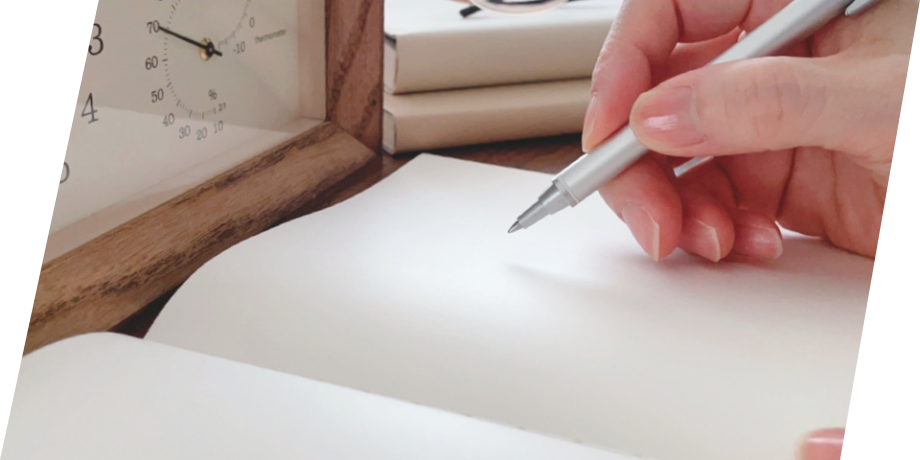
食品製造業におけるAI活用:生産性向上とコスト削減のための戦略

はじめに:なぜ今、食品製造業で「AIによる業務効率化」が求められるのか?
食品製造業界は、今、構造的な課題に直面しています。慢性的な人手不足と労働力の高齢化、深刻化する食品ロス問題、そして消費者や規制当局から求められる厳格な品質管理など、単なる業務改善では解決が難しい喫緊の課題が山積しています。
これらの課題は、これまでのように「経験と勘」に頼る従来のやり方では乗り越えられません。例えば、市場のトレンドが目まぐるしく変化する現代において、迅速な商品開発は企業の競争力を左右しますが、人間の経験だけでは対応しきれない状況です。
そこで、これらの課題を根本から解決するための「戦略的な武器」として、AI(人工知能)が注目されています。AIは、単なる未来技術ではなく、生産ラインから経営判断、マーケティングに至るまで、食品製造業のビジネスプロセス全体を再定義し、業務効率化、コスト削減、そして持続可能な成長を実現するための不可欠なツールとなりつつあります。
この記事では、「食品製造 業務効率化」というキーワードで情報を探している経営者や工場長、IT担当者に向けて、AIがどのように生産現場を変革し、どのような具体的なメリットをもたらすのかを、豊富な成功事例を交えて解説します。
1. AIが解決する食品製造現場の3つの課題
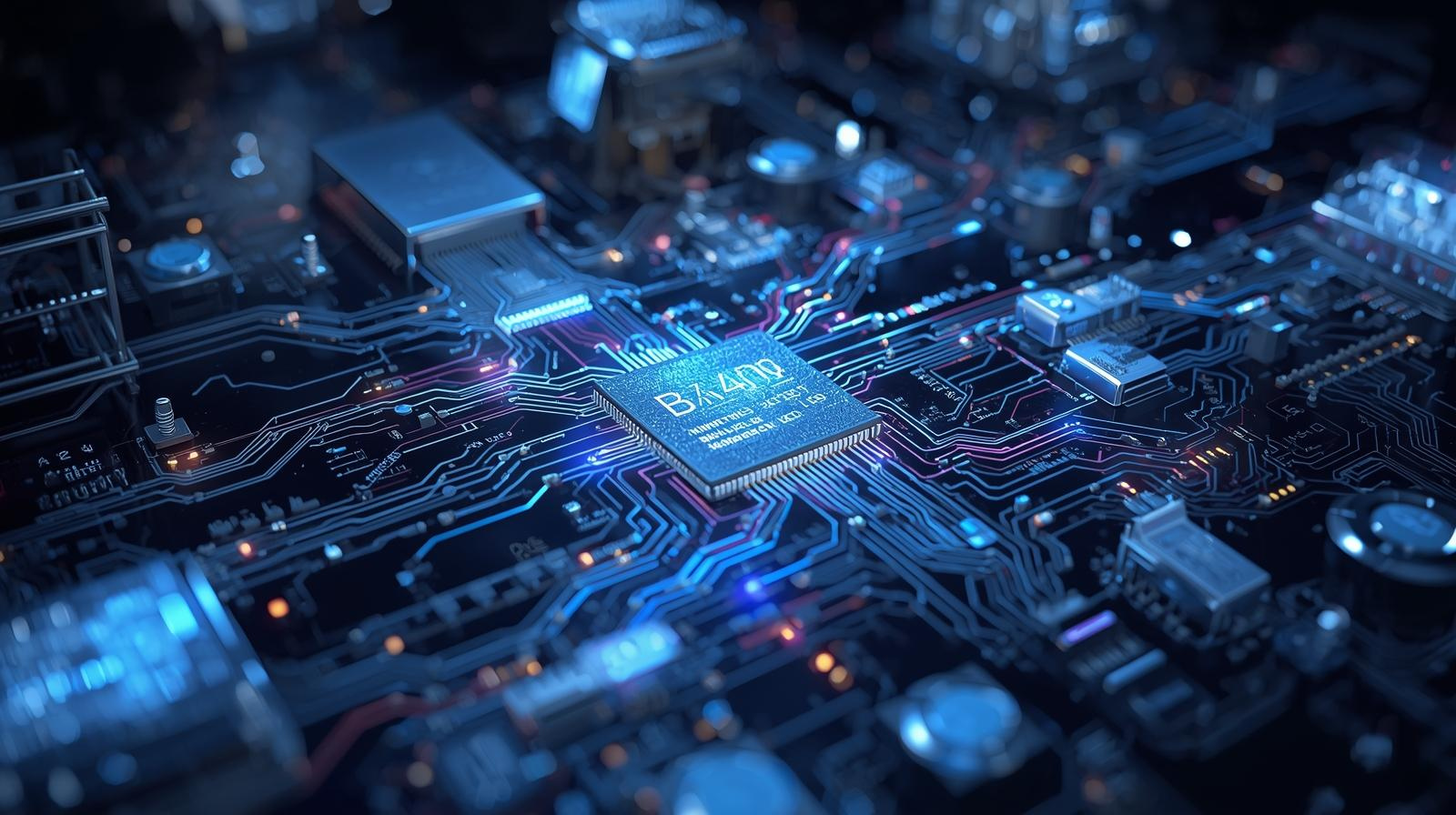
食品製造現場における業務効率化は、単に作業スピードを上げるだけではありません。AIは、以下のような構造的な課題を根本から解決することで、企業に持続的な競争優位性をもたらします。
1-1. 深刻な人手不足とベテラン依存からの脱却
日本の食品製造業界は、少子高齢化による労働人口の減少という長期的な課題に直面しています。特に、製造・生産ラインでの単純な手作業や、品質検査のような反復的な作業は、若い人材の確保が難しく、ベテラン従業員の経験と勘に依存する「属人化」が深刻な問題となっています。この属人化は、品質のばらつきや、新人教育に膨大な時間とコストがかかる原因となります。
AIは、この課題を以下のように解決します。
・自動化による省人化 タイソン・フーズの事例では、AIとロボット技術を融合して鶏肉処理工程を自動化し、年間2,000人分の労働力削減を見込んでいます。 また、キユーピーでは離乳食製造ラインにAI外観検査システムを導入し、手作業によるポテト選別を自動化することで、従業員の負担を大幅に軽減しました。
・人材育成の効率化 AIデータ社の「AI孔明™ on IDX」は、現場作業者の判断や手順確認をリアルタイムで支援するAI作業マネジメントです。 ベテランのノウハウを動画やチャット形式でデータ化し、タブレットやスマートフォンから簡単にアクセス可能にします。 これにより、新人教育期間が2週間から3日間に短縮できた事例も報告されています。多言語対応により、外国人労働者の立ち上がりもスムーズになります。
1-2. 食品ロス削減とコスト最適化
食品ロスは、世界的な環境問題であると同時に、企業にとっては生産・廃棄コストの増大と収益機会の損失に直結する大きな経済的課題です。過剰な生産や在庫は、そのまま企業の損失となります。
AIは、この二つの側面から課題を解決する独自性を持っています。
・高精度な需要予測: AIは、過去の販売データ、曜日、天候、イベント情報など、人間には処理しきれない膨大な要素を分析し、高精度な需要予測を行います。 これにより、必要な商品を必要な数だけ生産・発注する「適量生産」が可能となり、過剰在庫や欠品を防ぎます。 例えば、回転寿司チェーンのスシローは、AIを活用した需要予測システムでメニューの廃棄率を75%削減しました。 コンビニ大手のローソンも、AI発注システムによって廃棄ロスを約30%削減することに成功しています。
・在庫管理の効率化: AIは、在庫の賞味期限をリアルタイムで監視し、最適な在庫回転を促すことで、廃棄の発生を抑制します。 あるチョコレート製造会社では、需要予測システムの導入でフードロスを10%削減し、醤油製造会社では在庫管理の効率化で約15%削減に成功しています。 これらの事例が示すように、AIによる食品ロス削減は、企業の収益性と環境持続可能性を直接的に結びつける、強力なビジネスドライバーとなっています。
1-3. 品質管理の均一化と安全性向上
食品の安全性と品質は、企業の信頼を築く上で最も重要な要素です。しかし、人の目による目視検査には、見落としや検査精度のばらつきが生じるリスクが常に伴います。
AIは、この課題を以下のアプローチで解決し、企業ブランドを守ります。
・AI外観検査: AIを搭載した画像認識システムは、異物混入、不良品、包装の不備などを人間の目よりも高速かつ正確に検出します。 キユーピーでは、離乳食の原料であるダイスポテトの検査にAIを導入し、検査速度を2倍に向上させたほか、品質管理の属人化を解消し、安定した生産体制を構築しました。 大阪王将では、冷凍餃子の検品をAIが行うことで、1ラインあたりの生産量を2倍に増加させることに成功しています。 このように、AIは人間が集中力を維持するのが難しい単調な作業を代替し、品質の均一化と生産性の両方を向上させます。
・トレーサビリティの強化: AIとブロックチェーン技術を組み合わせることで、食品の生産から消費までの履歴を追跡可能にする「トレーサビリティ」を強化できます。 これにより、問題が発生した際に原因を迅速に特定できるだけでなく、消費者に製品の透明性を提供し、ブランドへの信頼を強固なものにします。
2. 注目すべきAI活用事例:成功企業に学ぶDX戦略

AI導入は、特定の企業規模に限定されたものではありません。大手企業が全社的なDXを推進する一方、中小企業も特定の課題解決に特化したAIを導入し、大きな成果を上げています。
2-1. 大手企業の生産現場におけるAI活用事例
・キユーピー: 離乳食製造におけるAI外観検査システムの導入は、検査速度を2倍にするだけでなく、従業員の負担を軽減し、品質管理の属人化を解消しました。
・大阪王将: 冷凍餃子の検品にAIを導入した結果、1パック(12個入り)の検品がわずか1秒で完了し、1ラインあたりの生産量を2倍に引き上げることに成功しました。 これは、AIが高速な反復作業において人間をはるかに凌駕する能力を持つことを示しています。
・ニチレイフーズ: 複雑な生産計画の立案にAIを活用し、計画作成にかかる時間を従来の約10分の1に短縮しました。 これにより、従業員はより価値の高い業務に時間を割くことができ、労働時間の低減や休暇取得率の向上にも貢献しています。
・キリンホールディングス: キリンビールは、新商品開発にAIを活用した「AIペルソナ」を導入しました。 これにより、従来の消費者インタビューに要していた時間を大幅に短縮し、消費者のインサイトを効率的に分析することで、市場ニーズに合った商品開発を加速させています。
・日清食品や味の素冷凍食品: 社内業務の効率化にも生成AIが活用されています。 日清食品は社内向けAIチャットボット「NISSIN AI-chat」を導入し、営業部門での商談記録の要約や提案書のドラフト作成などに活用。 味の素冷凍食品も同様に、社内データをAIに学習させることで暗黙知を共有資産化し、研究開発のスピードアップを図っています。
2-2. 中小企業でも実現可能なAI活用事例
・TUNA SCOPE: 熟練の職人の技術が必要だったマグロの品質判定を、AI搭載のスマートフォンアプリが代替する優れた事例です。 スマートフォンをかざすだけでマグロの断面を分析し、品質を4段階で評価します。 これにより、誰でも高品質なマグロを選別できるようになり、技術の属人化を解消しています。
・山村乳業: ChatGPTを商品開発に活用したユニークな事例です。 プリンバー開発で直面した技術的な課題に対し、ChatGPTに「物理の専門家」として相談することで、 人間だけでは思いつかなかった解決策を得て、新商品を開発しました。
・マルイ: 日配品の需要予測にAIを導入したところ、ロス率が97.5%も改善したと報告されています。 また、マルエツでもAIによる来店客数予測の精度が95%を超え、発注業務やシフト管理の効率化に繋がっています。 これらの事例は、AIが中小規模の小売業者や製造業者でも大きな経済的利益を生み出すことを証明しています。
・木村屋總本店: NECと共同で、若者の恋愛感情をAIが解析し、それを味で表現した「恋AIパン」を開発しました。 これは、AIを単なる効率化ツールではなく、マーケティングやブランド構築の領域にまで拡張した好例です。
3. 導入の障壁と成功のためのステップ

AI導入には、高額なコストや人材不足といった課題が伴います。しかし、適切な戦略とロードマップを描くことで、これらの障壁を乗り越えることが可能です。
3-1. 主要な障壁:費用、人材、そしてデータ
・高額な初期投資: ハードウェア、ソフトウェア、システム統合にかかる費用は、特に中小企業にとって「大きな障壁」となり得ます。
・専門人材の不足: AIシステムの開発、導入、運用ができる専門人材の確保が難しいことも、多くの企業が抱える深刻な課題です。
・データの課題: AIの有効性は、学習に用いるデータの質と量に大きく依存します。 データの正確性や偏りが、期待する結果に繋がらないリスクも考慮しなければなりません。 また、食品を扱うAIロボットには、厳格な衛生基準への対応が求められます。
3-2. 成功へのロードマップ:スモールスタートとノーコード/ローコード
AI導入の成功には、全社的な大規模改革を一度に行うのではなく、特定の部署や業務で小規模な実証実験(PoC)から始める「スモールスタート」が推奨されます。
(1)課題の明確化とスモールスタート: まずは「毎日の記録業務が負担」など、具体的な一つの課題に絞り込み、小規模な実証実験(PoC)から始めます。 これにより、初期投資のリスクを抑え、効果を段階的に検証できます。
(2)ツールの選定と活用: 専門知識がなくてもAIを活用できる「ノーコード・ローコード」ツールが増加しています。 これらのツールは、既存の業務システムと連携させることで、複雑なプログラミングなしに需要予測やレポート作成を自動化できます。
(3)補助金の活用: 国や地方自治体が提供する「IT導入補助金」や「DX推進補助金」を活用することで、導入費用の負担を軽減することが可能です。
(4)協業モデルの活用: AI開発を内製化するのではなく、外部のテクノロジー企業との提携や、業界コンソーシアムへの参加も有効な戦略です。 大手食品メーカー5社が結成したコンソーシアムのように、自社だけでは解決が困難な「非競争領域の共通課題」に共同で取り組むことで、 コストとリスクを分散させ、業界全体のデジタルトランスフォーメーションを加速させることができます。
4. まとめ:業務効率化を超えたAIの戦略的価値

「食品製造 業務効率化」を求めるユーザーの探求は、単なる効率の追求に留まりません。それは、人手不足を解消し、品質管理を強化し、食品ロスを削減することで、企業を持続可能な成長へと導くための戦略的な投資です。
AIの導入は、経済的圧力と社会的要請の収処によって推進される、経営戦略における根本的な転換点なのです。データ駆動型のアプローチに焦点を当て、小規模で管理しやすいプロジェクトから始め、協業の精神を受け入れることで、企業はAIを成功裏に統合し、コストを削減し、品質を向上させ、より持続可能で収益性の高い未来を築くことができます。AIは、単なる最適化ツールではなく、食品製造業自体を根本から変革する触媒なのです。
受発注バスターズ編集部
受発注バスターズ株式会社(旧:株式会社batton)は、AI搭載の業務効率化ツール「受発注バスターズ」やRPA「batton」の開発・提供を通じて、製造業・卸売業・商社の業務効率化とDXを支援しています。
「誰もが、仕事を遊べる時代へ。」をミッションに掲げ、属人化の排除や作業の自動化によって、人手不足やミスの多発といった現場の課題解決に取り組んでいます。
- 会社名:受発注バスターズ株式会社(旧:株式会社batton)
- 設立:2019年8月14日
- 所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目5-4 NOVEL WORK 京橋 3F
- 公式サイト:https://batton.co.jp/
※本記事は「受発注バスターズ編集部」が執筆・監修しています。