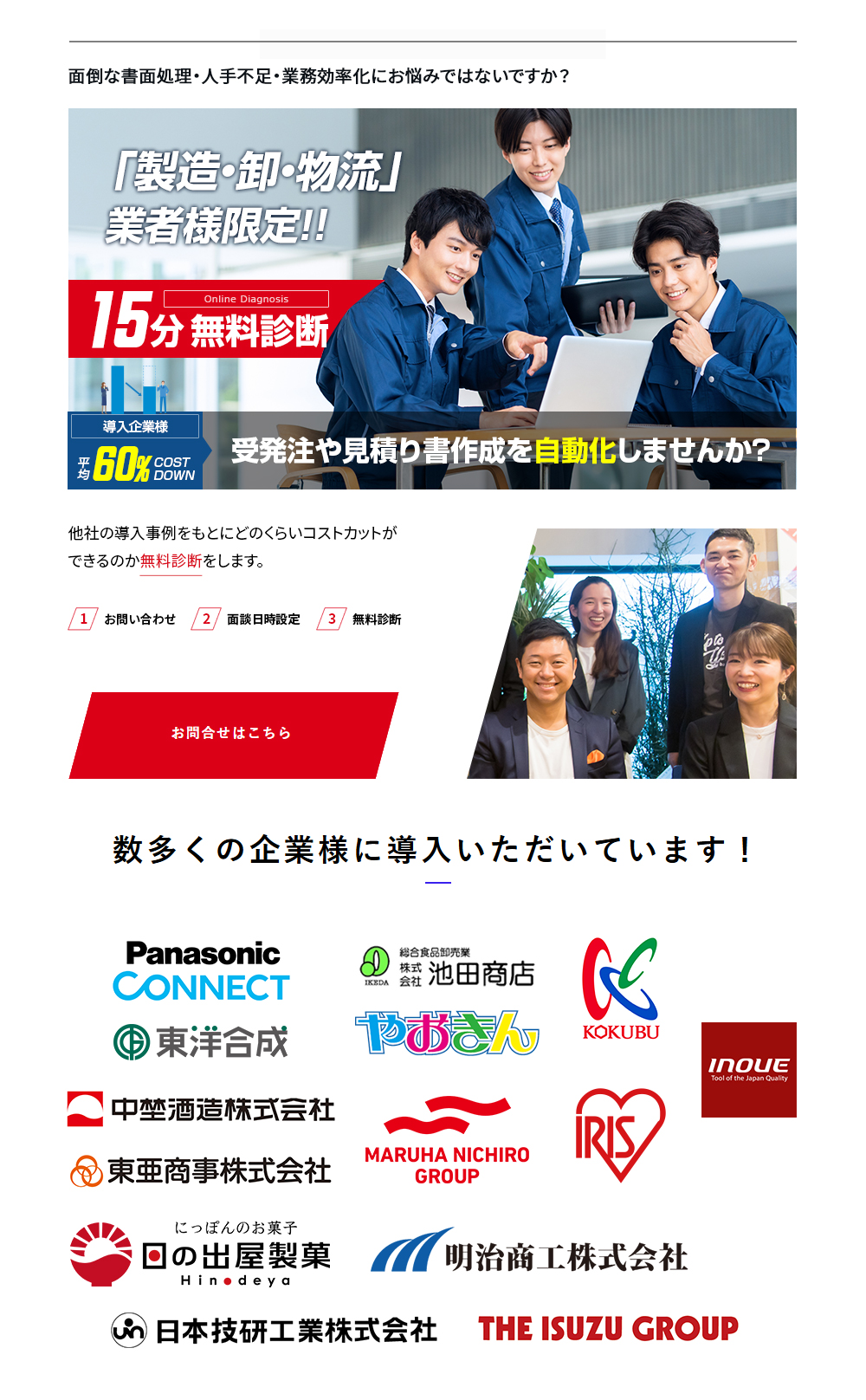コラム
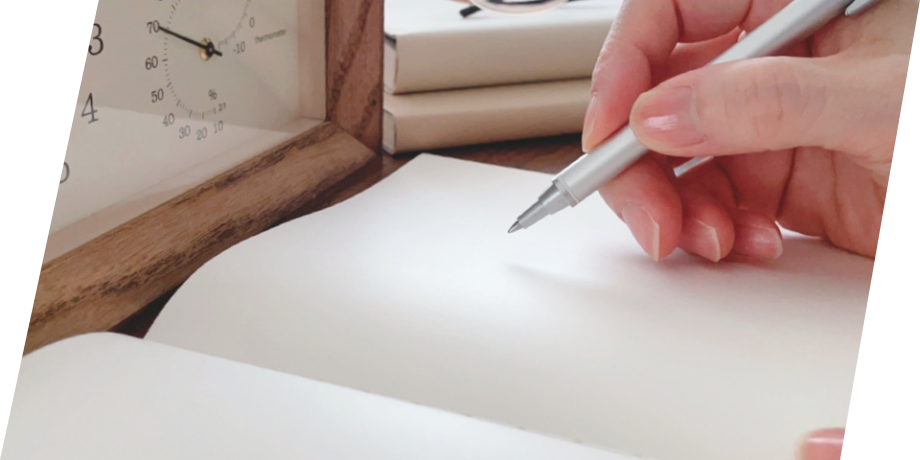
食品業界の中小企業こそDXを!課題解決から成功事例、補助金まで徹底解説

はじめに: 日本の食品業界におけるDXの現状と中小企業の課題、本記事で得られる価値
日本の食品業界は現在、多岐にわたる複合的な課題に直面しています。原材料の高騰、慢性的な人手不足、少子化による国内市場の縮小、消費者からの高品質・低価格要求の過多、そして深刻なフードロス問題がその代表例です。これらの課題はそれぞれが経営を圧迫する要因となりますが、特に中小企業においてはその影響がより顕著であり、抜本的な改革なくしては持続的な経営が困難になる可能性も指摘されています。
例えば、人手不足は生産性の低下を招くだけでなく、品質維持の困難さにもつながります。さらに、円安や原材料高騰は経営コストを押し上げ、利益を圧迫するため、従業員への待遇改善が難しくなり、結果として人手不足を一層加速させるという負の連鎖を生み出しています。このような状況下で、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、これらの複合的な課題を個別に解決するだけでなく、サプライチェーン全体の最適化やデータに基づいた迅速な経営判断を通じて、事業構造そのものを変革し、企業の競争優位性を確立するための不可欠な手段として位置づけられます。
しかし、食品製造業全体、特に中小企業におけるDXへの取り組みは、まだ普及途上にあります。大企業に比べて、中小企業ではDXの必要性に対する認識が低かったり、具体的な推進方法が分からなかったりする傾向が見られます。
本記事では、食品業界の中小企業が直面するDXの具体的な課題を深掘りし、それらを乗り越えるための実践的な解決策を提示します。具体的なDXソリューションの紹介、中小企業が参考にできる成功事例、活用可能な補助金・助成金、そしてDX人材の育成・確保、組織文化変革のポイントまで、網羅的に解説することで、中小企業がDX推進への具体的な一歩を踏み出すための道筋を示します。これにより、読者の皆様が「食品業界 DX」というキーワードで検索した際に求める、実践的で質の高い情報を提供することを目指します。
第1章: 食品業界中小企業が直面するDXの現状と課題

日本の食品業界におけるDXは、全体としてまだ発展途上にあり、特に中小企業においてその遅れが顕著です。この章では、その現状と中小企業が抱える具体的な課題を深く掘り下げていきます。
DX取り組み状況の遅れ:データで見る中小企業の現状
富士電機が2021年に実施した意識調査によると、食品製造業全体で「現在DXに取り組んでいる」と回答した企業はわずか13.6%に留まっています。この数字は、業界全体におけるDXの普及がまだ道半ばであることを示唆しています。
さらに注目すべきは、企業規模によるDX推進の格差です。従業員規模が小さい企業ほどDXへの取り組みが遅れていることが明確なデータとして示されています。具体的には、従業員100人未満の企業では「現在DXに取り組んでいる」と回答した割合が7.3%に過ぎず、これは従業員5000人以上の企業の34.9%と比較して27.6%もの大きな開きがあります。DXという言葉自体の普及も、従業員100人未満の企業では遅れている傾向が見られます。
また、中小企業においては、DXが「人手不足の解消や補完」に繋がるという期待が、大手企業(従業員1000人~4999人の企業で53.3%)と比較して低い(従業員100人未満の企業で10.5%)傾向にあります。このことは、中小企業がDXを単なるITツール導入と捉え、その本質的な価値、すなわちビジネスモデルの変革や経営課題の抜本的な解決に繋がる可能性を十分に認識できていない可能性があることを示唆しています。食品業界全体が慢性的な人手不足に直面しているにもかかわらず、中小企業がDXをその解決策として十分に位置づけられていない現状は、DX推進における意識のギャップが存在することを示しています。
中小企業特有の三大課題:人材不足、予算、知識・ノウハウの不足
DX推進における主要な障壁として、多くの企業が共通して「推進できる人材不足」(37.4%)、「予算の確保・制約」(34.3%)、「知識・ノウハウの不足」(34.3%)を挙げています。これらの課題は、特に中小企業において深刻な影響を及ぼしています。
従業員100人から499人の企業では、「知識・ノウハウの不足」が全体の平均よりも高い割合で課題として認識されており、DX推進に必要な専門知識や経験が不足している現状が浮き彫りになっています。これは、中小企業がDX推進を担う専門人材の確保が困難であることや、既存従業員への教育投資が十分に行き届いていないことと関連しています。
さらに、これらの課題は独立して存在するのではなく、相互に影響し合う関係にあります。例えば、人材不足が深刻な中小企業では、DX推進を主導する人材を確保することが困難となり、これが知識やノウハウの不足に直結します。また、予算の制約は、高価なDXソリューションの導入や外部の専門家を招聘することを阻害し、結果としてDXの遅れを招きます。この課題の相互依存性は、中小企業がDX推進において直面する「負の循環」を形成しており、単一の課題解決だけでは不十分で、多角的なアプローチが求められることを示しています。
富士電機の調査における自由回答形式の意見でも、「経営層の理解」や「現場へのDXの適用」といった課題が挙げられており、組織全体でのDXに対する理解と浸透の難しさが浮き彫りになっています。
「2025年の崖」とレガシーシステム問題
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」は、既存のレガシーシステムがDX推進の大きな障壁となる問題を指します。オンプレミス型やオフコンといった老朽化したシステムは、その保守運用に多大なコストがかかり、これが新たなDX投資を妨げる主要な要因となっています。
中小企業においては、IT人材の不足やIT投資への消極性から、特にレガシーシステムからの脱却が困難であるという実情があります。長年使い続けてきたシステムは、その複雑性やブラックボックス化が進み、改修や連携が困難になるだけでなく、セキュリティリスクの増大、データ活用の遅れ、そして競合他社とのデジタル格差の拡大といった深刻なリスクを顕在化させます。この「2025年の崖」は、単なるITシステムの課題に留まらず、中小企業の「存続」そのものに直結する喫緊の経営課題として認識されるべきです。
経営層の理解と現場への適用における障壁
DX推進の成否は、経営層の強いリーダーシップと明確なビジョンに大きく左右されます。しかし、前述の調査の自由回答でも示されているように、経営層のDXに対する理解が不足しているという課題が存在します。DXは単なるITツールの導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化そのものの変革を伴うため、経営層がその意義と目的を深く理解し、全社的なコミットメントを示すことが不可欠です。
また、DXを現場に適用する際の障壁も大きな課題です。現場の業務プロセスを正確に把握し、そのニーズに合致したシステムを開発すること、そして現場の従業員が新しいデジタルツールを使いこなし、その価値を実感できるような導入プロセスを設計することは容易ではありません。IT部門と現場部門間の連携不足は、導入されたシステムが現場のニーズと乖離し、結果としてDXが形骸化するリスクを高めます。これらの障壁を乗り越えるためには、経営層と現場、そしてIT部門が一体となってDXに取り組む体制の構築が求められます。
第2章: DXが食品業界中小企業にもたらす具体的なメリット
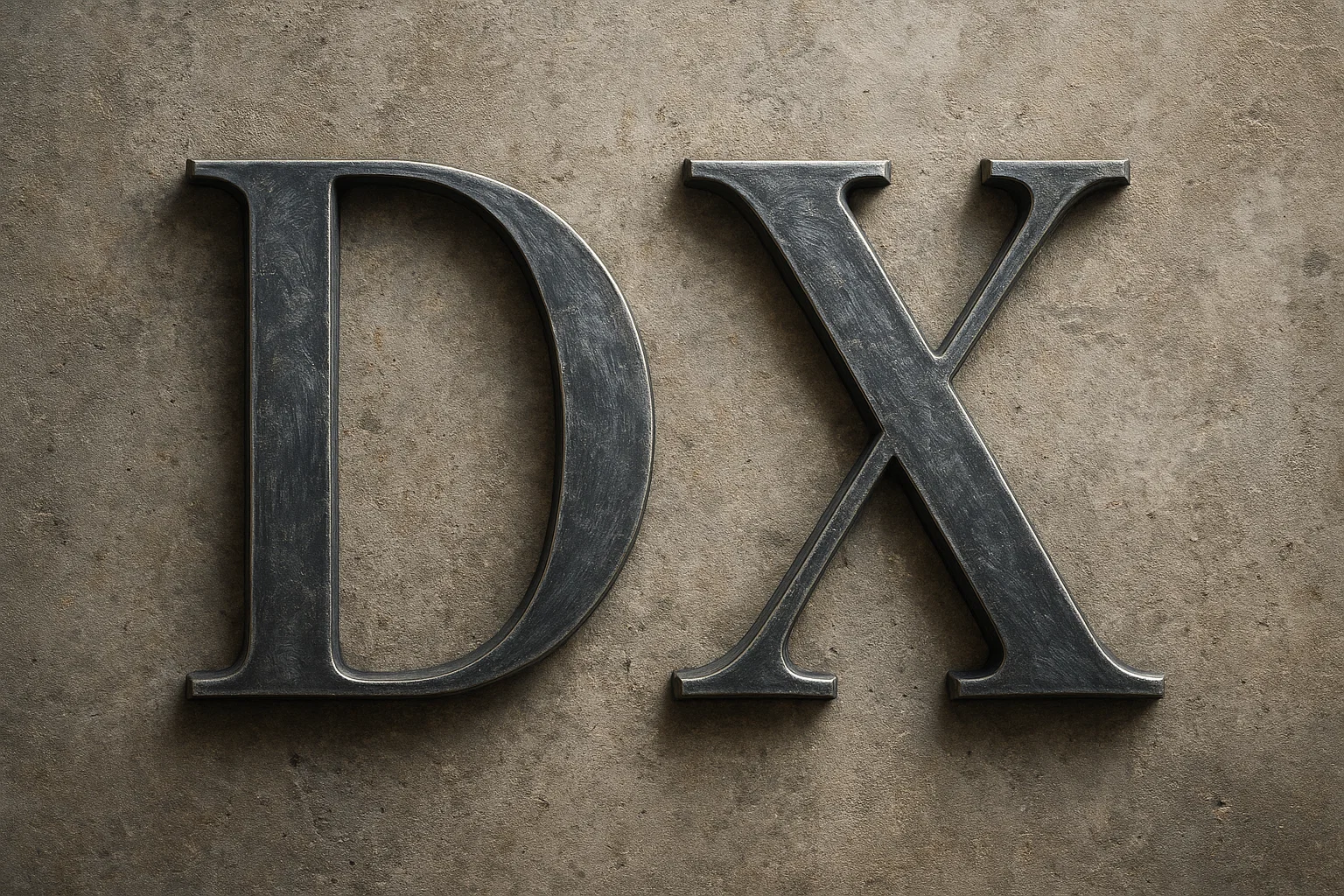
食品業界の中小企業がDXを推進することは、多岐にわたる経営課題を解決し、企業の持続的な成長と競争力強化に繋がる具体的なメリットをもたらします。DXは、単なる業務効率化に留まらず、ビジネスモデルそのものを変革する可能性を秘めています。
生産性向上と業務効率化
DXの導入により、AI、IoT、ロボット技術といった先端技術を活用することで、生産プロセスや事務作業の効率化・自動化が飛躍的に進展します。例えば、スマートファクトリー化は、生産ラインにおける人的ミスを大幅に削減し、生産性の向上に直接貢献します。
また、これまで紙ベースで行われていた生産スケジュール、作業マニュアル、従業員の勤怠・健康管理、品質管理記録、HACCP関連記録などのデジタル化は、業務負担を軽減し、情報共有の迅速化と効率化を実現します。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、全体の生産性向上が期待されます。
慢性的な人手不足の解消と労働環境の改善
食品業界が抱える最も喫緊の課題の一つが慢性的な人手不足です。DXは、この課題に対する強力な解決策となります。ロボットやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、繰り返し発生する定型業務や肉体労働を自動化することが可能になります。
具体的な事例として、サッポロビールではPOSデータのダウンロード作業にRPAを導入した結果、年間約1100万円のコスト削減と約5700時間の労働時間削減を実現しました。また、株式会社マツヤでは、ホテル購買システム「IPORTER」や企業間商取引のクラウドサービス「BtoBプラットフォーム」からの受注データダウンロード作業(WebEDI)をRPAで自動化し、わずか1ヶ月で106本もの自動化シナリオを開発、年間3,276時間もの業務効率化を達成しています。
これらの業務効率化は、人件費の削減に繋がるだけでなく、従業員の労働時間短縮や身体的・精神的負担の軽減にも寄与します。これにより、従業員満足度が向上し、結果として人材の定着率改善や新たな人材確保にも好影響をもたらすことが期待されます。DXは、人手不足という「負の連鎖」を断ち切り、従業員がより創造的で価値の高い業務に集中できる「正の循環」を生み出す可能性を秘めています。
品質管理の強化と人的ミスの削減
食品の安全と品質は、消費者の信頼を得る上で最も重要な要素です。DXは、この品質管理の精度を飛躍的に向上させ、人的ミスを削減する上で極めて有効です。AIやロボットが作業を代行することで、発注ミスや工程ミスといった人的エラーを未然に防ぐことが可能になります。
特に、異物混入検査のような精密な作業においては、人間の目では見落としがちな微細な問題も、機械学習を活用したAIやカメラシステムが正確に検出し、検査精度を向上させることができます。三島食品の事例では、BIダッシュボードを導入することで、温湿度管理、稼働状況、原材料の異物量、設備保全状況などをリアルタイムで可視化し、品質管理の効率化と迅速なトラブル対応を実現しています。また、ある調味料製造メーカーでは、原材料の計量、小分け、投入といった工程をシステム化したことで、計量ミスがゼロになり、製造前後の準備作業や手作業によるチェックなどの付帯作業が半減したと報告されています。これにより、品質の均一化と安定供給に貢献し、企業の信頼性を高めることができます。
食品ロス削減と需要予測の最適化
食品ロスは、環境問題だけでなく、企業の経済的損失にも直結する深刻な課題です。DXは、この食品ロス削減に大きく貢献します。AIによる高精度な需要予測システムを導入することで、過去の販売データや気象情報、イベント情報などを分析し、より正確な販売量を予測することが可能になります。これにより、過剰な生産を抑え、適正在庫を維持することで、廃棄される食品の量を大幅に削減できます。
さらに、鮮度予測技術の導入も食品ロス削減に貢献します。収穫時から流通過程における温湿度データなどを活用し、食品の鮮度を予測することで、鮮度に応じた価格設定を行ったり、消費期限が近づいた商品を家庭での消費を促したりするなどの施策が可能になります。これらの取り組みは、企業の経済的メリットだけでなく、SDGs(持続可能な開発目標)への貢献という社会的価値も創出します。
サプライチェーンの一貫管理とトレーサビリティ向上
DXは、食品の生産から消費者の手に届くまでのサプライチェーン全体を「見える化」し、一貫管理することを可能にします。IoT技術を活用することで、現場の生産状況や在庫状況、品質データなどをリアルタイムで収集・分析し、生産管理部門との連携を強化できます。
原材料の入荷から製品の出荷まで、工場内の物の動きをQRコードやRFIDなどの技術で管理するトレーサビリティソリューションを導入することで、紙の使用量を最大75%削減し、棚卸時間を25%短縮した事例も報告されています。これにより、製品の生産履歴や流通経路が明確になり、万が一問題が発生した場合でも迅速な原因究明と対応が可能となります。消費者は商品の情報を簡単に確認できるようになり、食品安全に対する信頼感が向上し、サプライチェーン全体の透明性と信頼性が高まります。
コスト削減と競争力強化
上記で述べた生産性向上、人手不足解消、品質管理強化、食品ロス削減は、結果として企業のコスト削減に繋がります。効率的な在庫管理や最適化されたサプライチェーンは、無駄なコストを削減し、利益率を高めます。また、ペーパーレス化は印刷費や搬送費の削減に貢献します。例えば、日本ハムではSmartHRの導入により、給与明細のペーパーレス化や本社と工場間の情報共有化が進み、コスト削減に繋がっています。
これらのメリットは、中小企業が厳しい競争環境の中で生き残り、持続的に成長するための基盤となります。DXは単なるIT投資ではなく、企業価値向上や持続可能性のための戦略的投資として捉えることで、市場での競争優位性を確立し、新たなビジネスチャンスを創出する鍵となるでしょう。
表1: 食品業界中小企業のDX課題と解決策の対応表
| 食品業界中小企業の主な課題 | DXによる解決策 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 人手不足、技能伝承の困難 | RPA、自動化ロボット、スマートファクトリー化、HRシステム導入、動画マニュアル | 業務効率化、人件費削減、労働時間短縮、従業員負担軽減、品質均一化、採用力強化 |
| 予算の制約、IT投資への躊躇 | クラウド型システム(SaaS)、IT導入補助金等の活用、スモールスタート | 低コストでのDX導入、初期投資の抑制、段階的な効果実感 |
| 知識・ノウハウの不足、DX人材不足 | DX人材育成プログラム、外部人材活用、DX人材マッチングプラットフォーム、IT導入支援事業者との連携 | 社内ITスキル向上、専門知識の補完、DX推進体制の強化 |
| レガシーシステム、データ連携の非効率性 | クラウドベースのERP導入、データ共有基盤構築、既存システムとの連携 | 保守運用コスト削減、データの一元管理、経営判断の迅速化、セキュリティ強化 |
| 経営層の理解不足、組織文化の変革困難 | 経営層のリーダーシップ、DX推進チーム設置、社員向けアンケート・発表会、小さな成功体験の共有 | 全社的なDX意識向上、当事者意識の醸成、変革への抵抗感低減 |
| 品質管理の属人化、人的ミス | IoT/AIによる品質管理システム、カメラセンサー、トレーサビリティシステム、BIダッシュボード | 検査精度向上、人的ミス削減、品質の安定化、食品安全性の確保 |
| 食品ロス、需要予測の困難さ | AIによる需要予測システム、クラウド型在庫管理システム、鮮度予測技術 | 適正在庫の維持、廃棄ロス削減、生産計画の最適化、環境負荷低減 |
| サプライチェーンの非効率性、透明性不足 | サプライチェーンマネジメントシステム、QRコード/RFIDによるトレーサビリティ | 全体最適化、情報共有の円滑化、消費者信頼の向上、問題発生時の迅速対応 |
| 営業・販路開拓の非効率性 | 営業DX(MA/CRM/SFA)、ECサイト構築、オンライン展示会活用 | 新規顧客獲得、既存顧客深耕、高利益体質化、市場競争力強化 |
第3章: 食品業界中小企業向けDX推進のステップと具体的なソリューション

食品業界の中小企業がDXを成功させるためには、闇雲に最新技術を導入するのではなく、自社の課題に合わせた戦略的なステップと適切なソリューションの選択が不可欠です。
DX推進の基本ステップ:スモールスタートと段階的アプローチ
DXは、一度に大規模なシステムを導入するのではなく、まずは小さな範囲から始めて成功体験を積み重ね、その効果を検証しながら段階的に拡大していく「スモールスタート」のアプローチが非常に有効です。このアプローチは、限られたリソースを持つ中小企業にとって、リスクを抑えつつDXのメリットを享受するための現実的な方法です。
最初のステップとして、紙ベースの業務のデジタル化や、特定の部門における定型業務の自動化(RPA導入など)から着手することが推奨されます。これらの小さな成功は、従業員のDXに対する理解を深め、協力を促し、全社的なDX推進へのモチベーション向上に繋がります。経営層が率先してDXに取り組む姿勢を示すことも、社員の当事者意識を醸成し、組織全体の変革を加速させる上で極めて重要です。
中小企業が導入しやすい主要DXソリューション
中小企業がDXを始めるにあたり、特に導入しやすく、かつ大きな効果が期待できる具体的なソリューションをいくつか紹介します。
クラウド型生産管理システム:低コストで始める生産効率化
クラウド型の生産管理システムは、自社でサーバーを管理・保守する必要がないため、IT人材が不足している中小企業でも比較的容易に導入できます。初期費用を抑えられ、月額利用料で手軽に始められる点が大きなメリットです。
市場には中小企業向けの多様なクラウド型生産管理システムが存在します。例えば、「スマートF」は、初期費用30万円から、月額4.8万円から利用可能であり、必要な機能からスモールスタートできる柔軟性が特徴です。130を超える設定機能で個別カスタマイズなしに柔軟な設定が可能で、既存システムとの連携も容易であり、250社以上の導入実績があります。また、「TECHSシリーズ」は、中小企業に特化した設計で、クラウド型の場合200万円から導入でき、4,300社もの導入実績を誇ります。これらのシステムは、生産計画、工程管理、資材管理などを一元化し、生産効率の向上とコスト削減に貢献します。
クラウド型在庫管理システム:リアルタイム在庫把握と食品ロス削減
在庫管理は、食品業界において品質維持と食品ロス削減に直結する重要な業務です。クラウド型在庫管理システムを導入することで、在庫の品目、保管場所、数量を容易に管理できるようになり、棚卸にかかる手間や時間を大幅に削減できます。手作業による入力ミスや計数間違いを減らし、実在庫とデータのズレを解消することで、より正確な適正在庫の維持に貢献します。
具体的な事例として、株式会社マスヤでは、スマートマットクラウド(SMC)を導入することで、給食用食材や梱包用品の在庫を工場に立ち入ることなく遠隔で管理できるようになり、週2回行っていた実地棚卸の負担を軽減し、発注確認の手間を削減しました。
低価格で利用可能なシステムも多く、例えば「FLAM」はシンプルで直感的な操作性が特徴で、月額9,300円から利用できます。また、「ZAICO」は月額980円から利用可能なプランがあり、200件までのデータ登録が可能な無料プランも提供されています。これらのシステムは、過剰在庫のリスクを減らし、食品ロス削減に貢献するとともに、従業員の負担軽減にも繋がります。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション):定型業務の自動化で人手不足を解消
RPAは、パソコン上で行われる繰り返し発生する定型業務をソフトウェアロボットが自動で実行する技術です。データ入力、ファイルダウンロード、メール送信、帳票作成など、人間が行うと時間と手間がかかり、ミスも発生しやすい業務を自動化することで、従業員の負担を軽減し、人手不足を補完します。
サッポロビールでは、POSデータのダウンロード作業にRPAを導入した結果、年間約1100万円のコスト削減と約5700時間の労働時間削減を実現しました。また、ホテルやレストランに食材を卸す株式会社マツヤは、WebEDIからの受注データダウンロード作業をRPAで自動化し、年間3,276時間の業務効率化を達成しています。
中小企業でも導入しやすいRPAツールとして、「BizRobo!」や「RoboTANGO」などがあります。これらのツールは、専門知識がなくても比較的容易に導入でき、短期間で業務効率化の効果を実感できる可能性があります。
IoT/AI活用:品質管理、需要予測、スマートファクトリー化の第一歩
IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)の活用は、食品工場のスマート化を推進し、品質管理の高度化や需要予測の精度向上に貢献します。IoTデバイスを通じて生産設備や環境データ(温度、湿度など)をリアルタイムで収集・分析することで、業務全体の「見える化」が実現し、改善点や最適化の機会を特定しやすくなります。
AIによる需要予測は、過去の販売データや市場トレンド、気象情報などを分析し、より精度の高い生産計画を立てることを可能にします。これにより、過剰生産や欠品のリスクを低減し、食品ロス削減にも大きく貢献します。
具体的な応用例としては、カメラセンサーを用いた自動検品システムや異物混入チェック、冷蔵庫の自動温度管理システムなどがあり、これらは品質管理の精度向上と省人化に繋がります。また、味の素グループのように、工場全体を3Dデータで再現するデジタルツイン技術を導入し、設備の配置や稼働状況をPCやタブレット上で確認できるようにすることで、効率的な生産管理と迅速な意思決定を実現している事例もあります。
その他:営業DX、HRシステム、情報共有ツールの導入
生産現場だけでなく、バックオフィス業務や営業活動においてもDXは効果を発揮します。
営業DX:
ソリューションサイトの構築や、MA(マーケティングオートメーション)、CRM(顧客関係管理)、SFA(営業支援システム)といったツールの導入により、新規顧客の獲得から既存顧客の深耕までを効率化できます。これにより、卸売り中心で利益率の低いビジネスモデルから脱却し、直接取引による高利益体質を目指すことが可能になります。
HRシステム:
SmartHRのようなHRシステムの導入は、給与明細のペーパーレス化、本社と工場間の情報共有の円滑化など、人事・労務業務の効率化とコスト削減に貢献します。
情報共有ツール:
社内ポータルサイトやWeb会議システム、動画マニュアル(tebikiなど)の導入は、社内コミュニケーションを円滑にし、情報共有の効率化、教育工数の削減、そして従業員のスキルアップに寄与します。
これらのソリューションは、中小企業が抱える様々な課題に対応し、DX推進の第一歩として有効な選択肢となります。
表2: 中小企業向けクラウド型生産・在庫管理システム比較表(抜粋)
| システム名 | 提供形態 | 初期費用相場 | 月額費用相場 | 主な機能 | 対象企業規模・特徴 |
| 生産管理システム | |||||
| スマートF | クラウド/SaaS | 30万円~ | 4.8万円~ | 生産計画、工程管理、資材管理、受発注管理、品質管理、原価管理、設備管理など | スモールスタート可能、130以上の設定機能で柔軟対応、既存システム連携、250社以上導入実績 |
| TECHSシリーズ | オンプレミス/クラウド | クラウド200万円~ | 要問い合わせ | 個別受注型や多品種少量生産に対応、業種や生産形態に合わせて選択可能 | 中堅・中小企業向きに特化、4,300社導入実績 |
| 在庫管理システム | |||||
| SmartMat Cloud (SMC) | クラウド | 要問い合わせ | 要問い合わせ | リアルタイム在庫可視化、遠隔管理、棚卸自動化 | 在庫管理DXに特化、マスヤなど食品製造業での導入事例あり |
| FLAM | クラウド | 要問い合わせ | 9,300円~ (3アカウント) | 在庫数管理、発注管理、在庫履歴閲覧など基本機能 | 低価格、シンプルで直感的な操作性、初めての利用でも使いやすい |
| ZAICO | クラウド | 無料プランあり | 980円~/月 (1ユーザー) | 在庫管理、複数人での共有、データ登録 | 31日間無料、データ登録200件までの無料プランあり、低価格で導入可能 |
※上記は抜粋であり、各システムの詳細な機能や価格は提供元にご確認ください。
第4章: 中小企業のためのDX成功事例

DX推進は、具体的な成功事例から学ぶことが最も効果的です。ここでは、日本の食品業界の中小企業がどのようにDXを導入し、課題を克服して成果を出したか、いくつかの事例を紹介します。これらの事例は、限られたリソースの中でもDXが実現可能であることを示唆しています。
在庫管理DXで業務効率化を実現した事例(株式会社マスヤ)
給食用食材や梱包用品の製造を手掛ける株式会社マスヤは、以前、製造現場に出向いて週2回の実地棚卸を行っており、その負担が課題となっていました。また、実在庫と棚卸結果に差異が発生することも多く、発注担当者がわざわざ工場内へ確認に行く手間も生じていました。
この課題を解決するため、同社はスマートマットクラウド(SMC)を導入しました。SMCの導入により、工場に立ち入ることなく遠隔で在庫を管理できるようになり、実地棚卸の負担が大幅に軽減されました。これにより、在庫の見える化が実現し、発注担当者の確認作業も不要になるなど、業務効率化に大きく貢献しました。この事例は、IoTを活用したクラウド型在庫管理システムが、中小企業の人手不足解消と業務効率化に直結することを示しています。
販売・プロモーションDXで新たな顧客接点を創出した事例(アイビック食品株式会社)
食品メーカーであるアイビック食品株式会社は、製造工程だけでなく、販売方法やプロモーション方法でもDXを推進している点が特徴です。同社は「GOKAN」という「食」に特化した最先端施設を完備しており、試食会や料理教室に活用できるセントラルキッチン、動画配信やライブ配信に対応できるオープンキッチン、商品や料理のスチール撮影ができるスタジオなどを備えています。
さらに、デジタルサイネージやVR/ARなどのデジタル設備を所有し、コロナ禍で打撃を受けた飲食事業者などを支援するために食の情報発信や商品開発を行っています。この取り組みは、デジタル技術を単なる業務効率化に留めず、顧客体験の向上や新たなビジネスモデルの創出に活用することで、市場における競争力を強化できる可能性を示しています。
社内DX推進チームで組織変革を成し遂げた事例(中田食品)
創業120年の梅干しづくり老舗企業である中田食品(和歌山県)は、デジタル時代に対応するために社内横断型のDX推進チームを結成しました。同社は、数値管理の重要性を認識し、「デジタルなくして成長はありえない」という強い危機感を持ち、各部署から選抜されたメンバーでチームを構成しました。
このDX推進チームは、全社の情報を共有しながら全体最適化を目指し、情報共有化のために社内ポータルサイトを開設するなど、具体的なICT活用を進めています。例えば、以前は紙文書で行っていた社有車使用時の運転日報の記録・提出・保管をアプリケーションで完結できる社内システムを構築し、今後義務化されるアルコール検知器の使用にも対応できるようにしました。この営業本部で蓄積されたノウハウは、DX推進チームを通じて社内全体で共有される予定です。この事例は、経営層の強い意思のもと、部門横断的なチームを組成し、小さな成功を積み重ねながら組織文化を変革していくことの重要性を示しています。
紙業務を削減し、コストとミスを削減した事例(株式会社共同)
食肉のトータル加工を請け負う株式会社共同は、DX導入前、紙での確認や指示による時間ロスと人的ミスが大きな課題でした。
この課題を解決するため、同社は倉庫管理システムを導入しました。このシステムでは、商品をバーコードで管理し、商品情報、保管場所、出庫指示まで行えるようにしました。このシステム導入により、倉庫から商品を探す労務コストや、類似商品との取り違えといった人的ミスが大幅に削減され、コストの大幅削減が実現しました。この事例は、既存の非効率な紙業務をデジタル化するだけでも、中小企業にとって大きな業務改善とコスト削減効果が得られることを示しています。
その他、中小企業に示唆を与える具体的な導入事例
また、製造前後の準備工程や手作業によるチェックなどの付帯作業が不要になり、トータル作業時間が半減したと報告されています。
これにより、無駄な作業がなくなった分、従業員は本来の作業に集中できるようになりました。
その結果、教育内容が統一され、OJTの教育工数も削減されました。
これは、デジタルツールが人材育成と品質の均一化に貢献する良い例です。
そこでWi-Fi環境を整備し、タブレットやバーコードスキャナーを使った出荷検品システムを導入した結果、作業効率の改善と人的ミスの削減に成功しました。
これは、既存のIT環境を改善するだけでも、DXの第一歩として大きな効果が得られることを示しています。
これらの事例は、大企業のような大規模なDXだけでなく、中小企業でも「スモールスタート」で着実に成果を出せることを示しています。自社の課題に合わせた適切なデジタルツールを選定し、段階的に導入していくことが、DX成功の鍵となります。
第5章: DX推進を加速させるための支援策とポイント

食品業界の中小企業がDXを成功させるためには、自社の努力だけでなく、外部の支援策を最大限に活用し、組織全体で変革に取り組むことが不可欠です。
活用すべき補助金・助成金ガイド
DX推進には一定の投資が必要ですが、国や自治体は中小企業のDXを支援するための様々な補助金・助成金制度を提供しています。これらを活用することで、初期投資の負担を軽減し、DXへの一歩を踏み出しやすくなります。
IT導入補助金:対象、補助率、上限額、申請のコツ
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、デジタル化やDXに向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する制度です。
・補助対象と補助率・上限額
◦ 通常枠:補助額50万円以下の部分は補助率3/4以内(小規模事業者は4/5以内)、50万円超~350万円の部分は補助率2/3以内です。
◦ インボイス枠:会計・受発注・決済の機能を2機能以上有するITツールの導入を推進し、補助額350万円以下の申請が可能です。
◦ デジタル化基盤導入枠:会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECサイト構築などのITツール導入を支援し、補助上限額は最大3,000万円(基盤導入経費+消費動向等分析経費)です。
◦ セキュリティ対策推進枠:サイバーセキュリティ対策を支援し、補助率は1/2、補助上限額は100万円です。
・申請のコツと採択率
◦ 自社課題と導入目的の明確化:単なるIT導入ではなく、自社の課題に対してどのような目的でどのITツールを導入するのかを明確に記述しましょう。
◦ 申請内容の整合性と不備の確認:目的・内容・期待効果の整合性を保ち、入力ミスや漏れがないようにチェックします。
◦ 加点・減点項目の意識:公募要領の審査項目を確認し、加点要素(セキュリティ対応、テレワーク支援など)をできるだけ盛り込みましょう。
◦ 信頼できるIT導入支援事業者との連携:採択実績のある事業者は、申請書作成のサポートや成功率を上げるノウハウを持っています。
◦ 早めの準備:GビズID取得には1~2週間かかることもあるため、余裕を持って準備を始めましょう。
IT導入補助金の採択率は、枠や時期によって変動しますが、例えば2025年の通常枠1次締切分では50.7%、インボイス対応類型では57.6%、セキュリティ対策推進枠では100%と報告されています。専門の支援事業者と連携することで、これらの平均採択率を上回る実績を出すことも可能です。
製造業DX推進事業補助金、中小企業省力化投資補助金
IT導入補助金以外にも、DX推進に活用できる補助金があります。
地域の中小企業支援機関が情報を提供しており、自治体の公募情報を定期的に確認する必要があります。
従業員数に応じて補助上限額が異なり、5人以下の企業で200万円、21人以上の企業では1,000万円まで。
さらに、賃上げを行う場合は補助額が増額される可能性があります。
食品包覆機(食品包あん機、餃子成型機等)なども補助対象の具体例として挙げられています。
これらの補助金は、中小企業がDX投資を行う上での大きな後押しとなります。
表3: IT導入補助金等、中小企業向けDX関連補助金概要(主要抜粋)
| 補助金名 | 目的・対象 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 備考 |
| IT導入補助金2025 | |||||
| 通常枠 | 中小企業・小規模事業者の労働生産性向上 | ITツール(ソフトウェア、サービス等)導入費 | 50万円以下: 3/4 (小規模4/5) 50万円超~350万円: 2/3 | 350万円 | デジタル化やDXを推進するITツール導入を支援 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | インボイス制度対応ITツールの導入促進 | 会計・受発注・決済機能を持つITツール導入費 | 2/3~4/5 | 350万円 | 会計・受発注・決済の2機能以上で補助 |
| デジタル化基盤導入枠 | 中小企業・小規模事業者のデジタル化推進 | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECサイト構築費、PC・タブレット等(10万円まで)、レジ・券売機等(20万円まで) | 1/2~4/5 | 3,000万円 (基盤導入+分析) | 複数機能の一体導入やEC対応が評価対象 |
| セキュリティ対策推進枠 | サイバーセキュリティ対策の強化 | サイバーセキュリティサービス利用料 | 1/2 | 100万円 | セキュリティ監査、従業員教育も重要 |
| 製造業DX推進事業補助金 | 製造業のDX推進、生産性向上 | DX推進に関わる設備投資、システム導入費等 | 2/3以内 | 500万円 | 地域によっては公募期間が限定される場合あり |
| 中小企業省力化投資補助金 | 人手不足解消、生産性向上 | IoT、ロボット技術等の汎用製品導入費 | 1/2 | 200万円~1,000万円 (従業員数による) | 賃上げで補助額増額、食品包覆機なども対象 |
※上記は主要な補助金の概要であり、詳細な要件や公募期間は各補助金の公式サイトでご確認ください。
DX人材の育成・確保戦略
DX推進の最大の課題の一つが「人材不足」です。この課題を克服するためには、既存従業員のスキルアップと外部人材の活用を組み合わせた多角的な戦略が求められます。
既存従業員のITスキル向上プログラムとオンライン研修
DX推進には、ITスキルを持つ人材が不可欠です。しかし、食品業界ではIT人材の不足が深刻な問題となっています。そのため、新たな人材を採用するだけでなく、既存従業員のITスキル向上のための教育プログラムを導入し、従業員のデジタルリテラシーを高めることが重要です。
研修内容は、導入するシステムに合わせた具体的な操作方法だけでなく、データ分析やセキュリティ対策に関する知識なども含めるべきです。外部機関との連携による専門的な研修も効果的であり、継続的な学習機会を提供することで、従業員のモチベーション向上にも繋がります。例えば、ニチレイグループは、グループDX戦略推進に向けて、2022〜2023年度にグループ社員約3,500名を対象にデジタル人材育成研修を実施し、デジタルリテラシーの習得を目指しています。このような大規模な取り組みだけでなく、DX推進のための要件定義研修やPythonプログラミング研修、ChatGPT×Excel研修など、中小企業でも導入しやすいオンライン研修プログラムも提供されています。
外部人材の活用とDX人材マッチングプラットフォーム
社内での人材育成には時間がかかるため、外部の専門人材を活用することも有効な手段です。DXコンサルタントやフリーランスエンジニアなど、特定のプロジェクト期間だけ専門知識を持つ人材を招き入れることで、DX推進を加速させることができます。
近年では、DX人材と企業を繋ぐマッチングプラットフォームも登場しています。デル・テクノロジーズは、中堅中小企業のDXを加速する産学連携のマッチングプラットフォーム「DXイノベーションコネクト」を提供しています。また、埼玉県では、DX相談からITパートナーマッチング支援までを無料で提供する取り組みも行われています。食品業界に特化した転職支援サービス「フーズラボ」のように、食産業に特化した採用DXプラットフォームも存在し、企業が自社に共感・マッチした人材をピンポイントで採用できるよう支援しています。これらのプラットフォームは、中小企業がDX人材を効率的に確保するための貴重なリソースとなります。ただし、一部のマッチングプラットフォームでは初期費用や月額料金が発生する場合があるため、費用対効果を考慮した上で利用を検討する必要があります。
現場とIT部門の連携強化
DX推進において、現場部門とIT部門の連携は極めて重要です。現場のニーズを正確にIT部門に伝え、IT部門は現場の業務プロセスを深く理解した上でシステム開発を行う必要があります。部署横断的にDXを進めるためにも、両部門間の定期的なコミュニケーションを図り、情報共有をスムーズに行う仕組みを構築することが重要です。例えば、プロジェクトチームを編成し、現場担当者とIT担当者が一体となって参加することで、より現場のニーズを反映したシステム開発を実現できます。
組織文化の変革と経営層・従業員の巻き込み方
DXは単なる技術導入ではなく、組織文化の変革を伴う取り組みです。この変革を成功させるためには、経営層の強いリーダーシップと、従業員一人ひとりの当事者意識の醸成が不可欠です。
経営層のリーダーシップとビジョン共有
DX推進の成功には、経営層がDXの意義を深く理解し、明確なビジョンを社内外に共有することが最も重要です。経営者自身がデジタル技術への関心を持ち、場合によっては自らプログラミングを学ぶなどしてリーダーシップを発揮することで、社員も意識を変えるという好循環が生まれます。DXは「システムを導入すること」自体が目的ではなく、「業務改善を通じて新たな価値を創造すること」であるという文化を醸成することが求められます。
社員の当事者意識を醸成する取り組み
従業員がDXを「自分ごと」として捉え、積極的に関与することが成功の鍵となります。そのためには、社員向けのDXに関するアンケートを定期的に実施し、現場の意見やアイデアを吸い上げる仕組みを設けることが有効です。また、DX推進チームを設置し、各部署から選抜されたメンバーが参加することで、部門間の連携を強化し、全社的な視点でのDXを推進できます。
使いやすいアプリの開発(例:お弁当発注アプリ、購買管理システム、生産計画アプリ)や、小さな成功体験を積み重ね、それを社内で定期的に発表・共有する場を設けることも、従業員のモチベーション向上とDXへの理解促進に繋がります。
小さな成功体験の積み重ねと情報共有
中小企業においては、大規模な投資や一足飛びの変革は難しいのが現実です。そのため、前述の「スモールスタート」の原則に基づき、まずは紙書類のデジタル化や特定の定型業務の自動化といった、比較的小さなDXから着手し、具体的な成果を出すことが重要です。
これらの小さな成功体験を社内で積極的に共有することで、「DXは自分たちにもできる」「DXは効果がある」という認識が広がり、次のステップへの意欲を高めることができます。情報共有の仕組みを整え、成功事例だけでなく、課題や改善点もオープンに議論する文化を醸成することが、持続的なDX推進の土台となります。
まとめ: 食品業界中小企業のDXは「今」がチャンス!未来を切り拓くために

日本の食品業界、特に中小企業は、人手不足、原材料高騰、市場縮小、品質要求の高度化、フードロスといった複合的な課題に直面しており、これらは企業の存続を脅かす喫緊の経営課題となっています。DXは、これらの課題を抜本的に解決し、企業の競争力を強化し、持続的な成長を実現するための不可欠な戦略です。
現状、中小企業におけるDXの取り組みは大手企業に比べて遅れており、人材、予算、知識・ノウハウの不足が主な障壁となっています。また、「2025年の崖」に象徴されるレガシーシステムの問題も、中小企業にとって無視できないリスクです。しかし、これらの課題はDXによって克服できるものであり、DXは単なるIT投資ではなく、企業価値向上と持続可能性のための戦略的投資として捉えるべきです。
DXがもたらすメリットは多岐にわたります。生産性向上と業務効率化、RPAによる慢性的な人手不足の解消、IoT/AIを活用した品質管理の強化と人的ミスの削減、AIによる需要予測を通じた食品ロス削減、サプライチェーンの一貫管理とトレーサビリティ向上、そしてこれら全てに起因するコスト削減と競争力強化が挙げられます。これらのメリットは、中小企業が直面する「負の連鎖」を断ち切り、「正の循環」を生み出す可能性を秘めています。
DX推進の第一歩として、中小企業は「スモールスタート」と段階的アプローチを推奨します。クラウド型生産管理システムや在庫管理システム、RPAツールなど、低コストで導入しやすいソリューションから着手し、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。
さらに、DX推進を加速させるためには、国や自治体が提供するIT導入補助金などの支援策を積極的に活用し、初期投資の負担を軽減することが賢明です。同時に、既存従業員のITスキル向上プログラムやオンライン研修、外部DX人材の活用、そしてDX人材マッチングプラットフォームの利用を通じて、人材不足の課題を克服する必要があります。
最も重要なのは、組織文化の変革です。経営層がDXの明確なビジョンを掲げ、リーダーシップを発揮すること、そして従業員一人ひとりがDXを「自分ごと」として捉え、積極的に関与できるような環境を整備することが不可欠です。社員向けのアンケートやDX推進チームの設置、小さな成功体験の共有を通じて、組織全体でDXを推進する文化を醸成していく必要があります。
食品業界の中小企業にとって、DXはもはや選択肢ではなく、未来を切り拓くための必須戦略です。今こそDXへの一歩を踏み出し、変化の激しい時代を乗り越え、持続可能な成長を実現する「強い企業」へと変革を遂げる絶好の機会であると言えるでしょう。
受発注バスターズ編集部
受発注バスターズ株式会社(旧:株式会社batton)は、AI搭載の業務効率化ツール「受発注バスターズ」やRPA「batton」の開発・提供を通じて、製造業・卸売業・商社の業務効率化とDXを支援しています。
「誰もが、仕事を遊べる時代へ。」をミッションに掲げ、属人化の排除や作業の自動化によって、人手不足やミスの多発といった現場の課題解決に取り組んでいます。
- 会社名:受発注バスターズ株式会社(旧:株式会社batton)
- 設立:2019年8月14日
- 所在地:〒104-0032 東京都中央区八丁堀3丁目5-4 NOVEL WORK 京橋 3F
- 公式サイト:https://batton.co.jp/
※本記事は「受発注バスターズ編集部」が執筆・監修しています。